サッカー育成年代における日本とスペインの違い〜部活とクラブのあり方〜

育成年代のサッカーの日本と海外の違いは?
部活とクラブチームどちらがいいの?
育成年代でどんなサッカー経験をさせるべきか、将来を考えると悩ましいですよね。
世界で活躍するサッカー選手になれるよう、できるだけ良い環境で子どもにサッカーをさせたいと思う人も多いはず。
本記事はスペインでホペイロとしてサッカークラブに所属した筆者が、スペインと日本のサッカー育成年代の違いについて解説します。
部活制の日本、クラブチーム制のスペイン


日本の子どもたちから見たサッカーは、
サッカー=学校の部活
というイメージが強いのではないでしょうか。
中学、高校はサッカー部だった!
という人、よく見かけると思います。
サッカーをしたい!と思ったら、学校の部活に入って放課後にサッカーをする、と考えるのはよくあることです。
一方でスペインには部活という概念がありません。
サッカー=クラブチーム
なのです。学校は関係ありません。
サッカーをしたい!と思ったら、今シーズンはどこのクラブに所属しようか、と考えます。
スペインの子どもたちがプレーするチームを選ぶ基準
スペインではクラブチームを選ぶ際に、
- 自分はどこに住んでいるのか
- 自分はどの学校に通っているのか
はあまり考慮に入れる必要はありません。
(もちろん家庭の都合により、家の近くにあるクラブを選ぶ場合も多くあります。)
スペインの子どもたちがクラブチームを選ぶときに考えるのは、
- どのリーグでプレーするクラブチームに入るのか
- どんな指導者がいるのか
- どんなチームメイトと一緒にサッカーをするのか
これらを重視して、自分にあったクラブを選ぶことが出来るのです。
先日12、13歳の子たちのチームのアウェイ試合に帯同した際、別の地域(別の市町村のようなもの)のクラブを訪れたときのこと。
選手の1人が相手チームの子と仲良く話していたので、「お友だちなの?」と聞いてみると、
あいつは学校の友だちだよ!
と言ってました。
20km以上も離れた場所にあるチームで学校の友だちに会う、なんてことも普通です。
部活の大会を中心に戦う日本、リーグを戦うスペイン
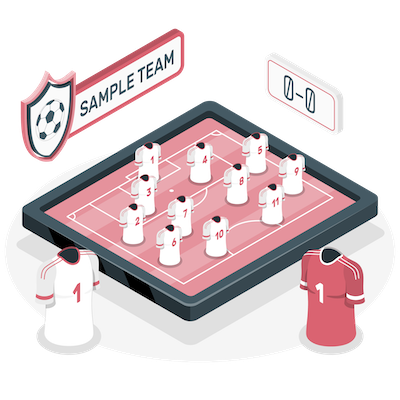
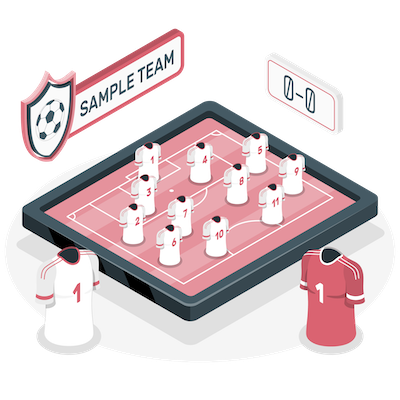
トーナメント戦や短期間のカップ戦が多い日本
部活の大会を中心としてサッカーの試合をする日本。
部活の主要な大会
- 全国中学校・高校サッカー大会(総体)
- 全国高等学校サッカー選手権大会
- 地区別中学・高校サッカー新人戦大会
その他自由参加のトーナメント戦、〇〇フェスティバル、〇〇カップなど
日本の育成年代のサッカーの公式戦はトーナメント制が多く、勝ち進んだチームが優勝する形式が多いですよね。



負けたら終わり(または引退)という大会に何度涙したか
ゴールデンウィークや夏休み、連休などは近隣の県や市に遠征して、地域の〇〇カップに参加することも。
大会がない週末は他のチームと練習試合を組むことが一般的だと思います。
リーグ戦を長期間戦うスペイン
スペインでは毎シーズンをリーグ戦で戦うことが当たり前です。
スペインのリーグ戦のスケジュール
- 8月後半からプレシーズン開始(平日はクラブで練習、土日は練習試合)
- 9月頃にリーグ戦開幕、毎週末ホーム&アウェイ方式のリーグの試合が始まる
- クリスマスや年末年始、イースター休暇に一旦ストップ
- 4〜5月頃にリーグ戦が終了
- 5〜6月はポストシーズンで来シーズンのチーム決め



有力選手はシーズン後半頃から来シーズンのオファーが始まります
毎週末のリーグ戦の結果が数字となって公式に表れ、勝ち点を競いながら順位を争います。
ホーム&アウェイ方式なので、同じリーグ内のチームと2試合ずつの対戦。
相手チームを分析しながら、戦術を変えて戦ったり、
昇格を目指して戦ったり、残留のために戦ったり。



1位を維持しながら戦い続けるのって大変
リーグ戦に合わせて毎週組まれる練習メニュー
週末の公式戦に合わせて、平日は練習メニューを組みます。
例えば火木金で週3日の練習であれば、
練習メニューの概要
- 火曜日……試合の振り返りやフィジカルトレーニング重視の練習
- 木曜日……週末の試合に向けて実戦形式のトレーニング
- 金曜日……木曜日の練習の修正や週末に向けて疲れを残さないトレーニング
といった風にメニューを組むことも出来ます。
上記の練習を毎週、1シーズン繰り返すのです。早い子では4〜6歳の段階で。



そりゃリーグ戦の戦い方を自然と覚えるようになるわ


カテゴリー別にリーグの戦い方が違う
スペインの育成年代は、年齢別でカテゴリーが分かれます。
| カテゴリー | 対象年齢 | 試合形式 |
|---|---|---|
| Juvenil(フベニール) | 17-19歳 | 11人制サッカー |
| Cadete(カデテ) | 15-16歳 | |
| Infantil(インファンティル) | 13-14歳 | |
| Alevin(アレビン) | 11-12歳 | 7人制サッカー |
| Benjamin(ベンハミン) | 9-10歳 | |
| Prebenjamin(プレベンハミン) | 7-8歳 | |
| Promesa(プロメサ) | 4-6歳 |
ちょうどわたしが帯同しているチームはInfantil Bチーム。
11人制サッカーに変わってから1年目の子どもたちです。
そんな彼らの指導をしているコーチとよく話すのですが、言われていることは
このInfantilカテゴリー1年目のシーズンは、11人制サッカーを学ぶことが目的だということ。
11人制になって初めて戦うフォーメーションや戦術。
グラウンドも前年の倍の広さ。
そんな状態で戦う子どもたちの主要目的は、11人制サッカーに慣れること。
もちろん1年目の段階でも、同じリーグ内に2年目の選手が揃ったチームが属していれば、格上の相手に挑戦を挑むことだって出来ます。
自分たちが学んできたことを生かしてみるチャンスにもなるわけです。
そしてInfantilカテゴリー2年目のシーズンはAチームとして、クラブの看板を背負いリーグ戦の順位を重視して戦っていきます。
こういった流れを、カテゴリーが上がるごとに選手たちはこなしていくんですよね。



そりゃ11人制サッカーの戦い方を効率よく覚えていくわ
日本サッカーの育成にも、クラブチーム×リーグ戦を取り入れるべきだ
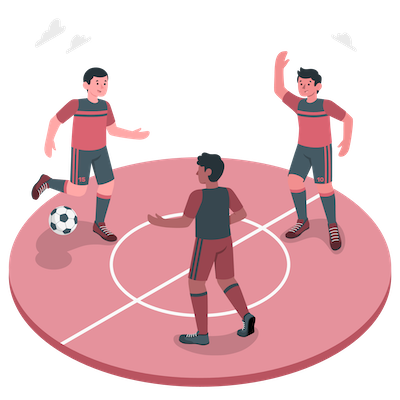
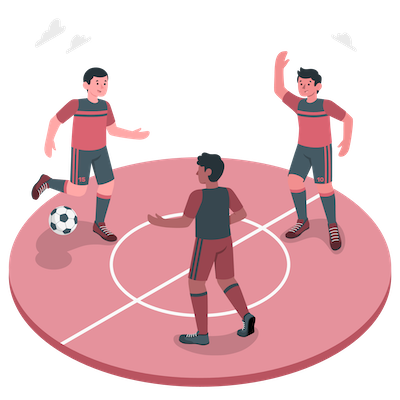
スペインのリーグ戦を1年間経験してみて、感じたこと。
それはリーグ戦を通して勝負に挑む機会が増えたり、計画的にサッカーに取り組んだりすることは、子どもたち1人ひとりの向上心にも繋がるのではないかということ。
しかしスペインのように、リーグ戦を日本全国各地で取り入れるのは簡単なことではない、というのも重々承知しています。
- 部活制からの離脱が難しい
- 地域によってはサッカー人口が多くない
- 全体的にクラブチームがあまりない
- サッカーは戦いではなく楽しむものだ、という考えがある
……
ですが、学校の部活というのは今日教員の時間外労働など様々な理由から反対の声も上がっています。
この流れを機に、日本サッカーも部活制からクラブチーム制へ移行するのが良いかもしれません。
育成年代の頃から先を見据えて、
クラブチーム×リーグ戦
を日本サッカーの育成にも取り入れるべきなのです。
こうしてクラブチームが増えて強くなっていけば、
- Jリーグに進出するクラブが出てきて日本サッカーが切磋琢磨される
- 地域ごとにおけるサッカーの発展も見込まれる
- 地方にクラブチームが出来てサポーターやファンが増えていけば、地方の活性化にもつながる
……
これらのことが可能になるかもしれません。
あなたはクラブチーム制への以降についてどう思いますか?
※日本のサッカーは部活だけでなく、クラブチームもきちんと活動しているということは承知しております。
ですが今回の記事では、部活としてサッカーに取り組む人が多いという点について取り上げていますので、あらかじめご了承頂けますと幸いです。
Muchas gracias por leer♡




